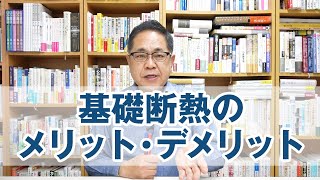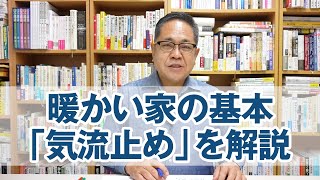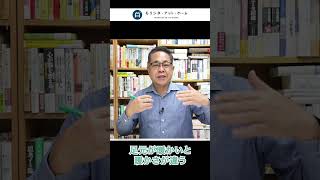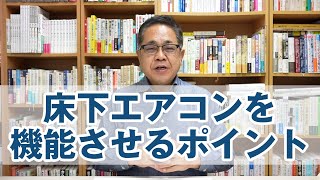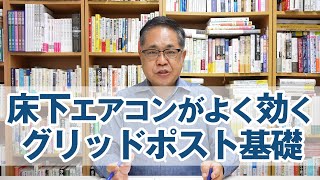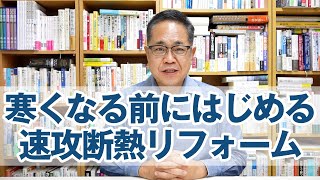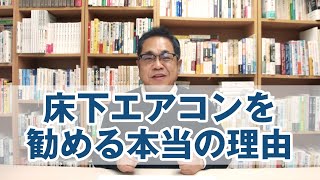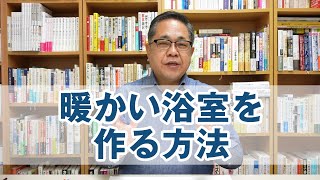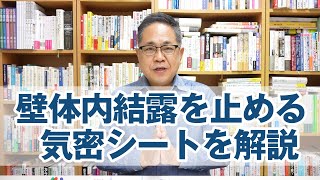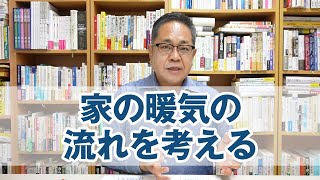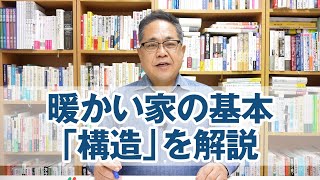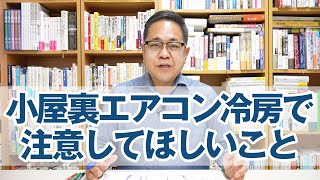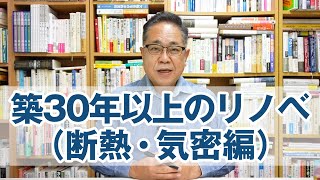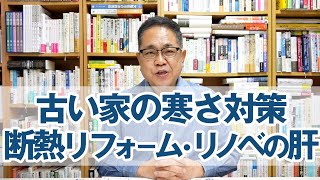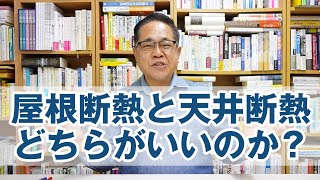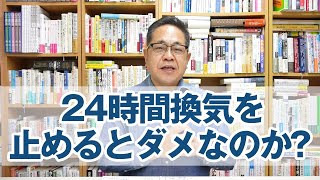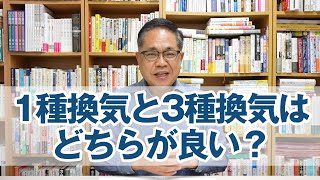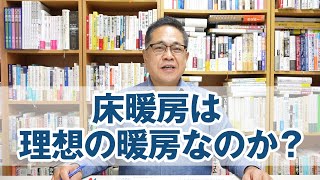基礎断熱のメリット・デメリット |

|
|
今日のテーマは基礎断熱のメリット・デメリットです。
基礎断熱と言うぐらいだから「他の断熱があるのかな?」と思われますよね。よく比較されるのは床断熱になります。 僕のスケッチを見てください。 断熱材は人間の住む居住空間の全てをぐるっと包んでいます。壁・天井はもちろん床も断熱材が入っています。 昔の古い木造住宅で、冬は畳の上でも寒いとか、板の間がすごく冷たいって言われるのは床に断熱材が入ってないからです。畳は一種の断熱材みたいなものではありますが、いかんせん厚みが50〜60mmぐらいしかないです。気密も取れないのもあって寒い家になっていました。 床断熱に対して登場したのが、基礎断熱になります。簡単に言うと、基礎の部分を断熱するということです。昭和50年代に北海道のような寒冷地用の汎用断熱仕様ということで生まれた技術と言われています。 寒い地域の人が選んだ断熱なんですね。床断熱ではなく基礎断熱というのが興味深いです。 基礎断熱はどんな形かを説明します。 同じ形の基礎の断面を描きました。外気が侵入しないよう、基礎の外側に断熱材を使うやり方もあれば、内側にL型にして、立ち上がりと少し入ったところに断熱材を使うこともあります。すごく寒い地域だとベタ基礎の底面全部に断熱材を使うこともあります。下から来るであろう冷気をカットするんですね。そういうやり方を総称して基礎断熱と言います。 なので「基礎断熱」と一言で言っても、基礎の外側に断熱材を使う基礎外断熱と、基礎の内側をやる基礎内断熱の2つがあるんだということを知っておいてください。 モリシタがある姫路のように本州の6地域とか5地域は基礎内断熱をしているケースが多いと思います。一方、東北とか北海道に行くと基礎外断熱をしていることが多いと思います。もしかすると両方しているところもあるかもしれませんが、さっき挙げたようなケースがが多いと思います。 なぜそういう成り立ちになったかというのをお話します。床断熱を昭和50年代に北海道で実践しようというときに1つメリットがあったんですね。 床断熱をすることで床下を含む家の全体の温度の安定化が図られたという結果がでたそうです。 というのも、スケッチに描いたような断熱材の使い方だとコンクリートが一部出ますよね。みなさんご存知のように、コンクリートは熱容量が大きいです。温まりにくいですが、一旦温まったら冷めにくいという特性があります。 鉄筋コンクリートのマンションの最上階だと昼間にガンガン日が照ったら、夜に寝苦しいということがあります。これはコンクリートが蓄熱してるので寝苦しいんですよね。逆に冬場、コンクリートが一旦冷えると、今度はなかなか温まりにくいです。なので室内で暖房をしても寒いです。冷輻射が起きています。 逆の意味でいい風に使えることもあります。床下空間を室内と同じ環境で使えるので、床下エアコンとの相性がいいです。僕は個人的に、これが最大のメリットかなと思っています。 一方で床断熱は基礎断熱と比較して気密が取りにくい、という面があります。 昔の家には大引きという太い土台があって、床の根太というのをクロスにして置いて、その上に床板を貼っていました。このときクロスにしたところに隙間ができるんですね。なので、ここの間にうまいこと断熱材を切り込んでも、壁際とか間仕切りの側で気流が入りやすいということがあります。もちろん気流止めもしますが、一般的には床断熱の方が気密が取りにくいです。今は根太レス工法に変わったので、気密性もずいぶん変わったと思いますが、それでもこういった一面があります。 基礎断熱のメリットに戻ります。水道管が凍結しにくいです。水道管って大体床下を通して上がることが多いので水道管が凍結しにくくなります。床断熱だと外気が基礎の中に入っていくので、外がものすごく温度が下がった時には、水道管の凍結もあり得ると思います。姫路ではあまり無いですが、北海道とか長野みたいに寒い所だったらあり得ます。 今度は基礎断熱のデメリットになります。 床断熱より少し金額が高いと言われています。ただ気密工事のことを考えると、そんな極端な差はないと僕は思います。最大のデメリットはカビや結露が発生する可能性があるかもしれないということです。 コンクリートは竣工して1年ちょっとぐらいは水分が出ます。また基礎断熱で床下が器のようになっています。床断熱だったら風が入って乾いていきますが、基礎断熱だと狭い空間に水分が保持されるようになるんですね。なのでカビができやすかったり、結露になる可能性があったり、ひょっとしたら結露が原因で白アリが湧くということもあります。 特に基礎外断熱をやる場合、忌避剤が入ってる樹脂のパネルを使いますが、最近はシロアリがそれも食い破って上がるという例が多いみたいです。なのでシロアリに弱いんじゃないかなと思ってデメリットに挙げました。なので僕たちは基礎外断熱をしています。西日本は北海道と比べるとシロアリがすごい多いので。 もう1つのデメリットは、床下に食品が置きづらいことです。 例えば床断熱だと点検口とか床下収納があって、床下は結構温度が低いので梅酒とか梅干し、お味噌とかの保管ができていました。 一方で基礎断熱で、さらに床下エアコンなどしていたら床下の温度がすごい上がるので食品が傷むかもしれませんので、気を付けてください。 最後に2022年4月からUA値の性能の外皮計算の基準が少し変わりました。従来と全く同じスペックで基礎断熱をしても、UA値上の評価は低く見るという風にルールが変わります。なので同じ家でも新計算基準でやるとUA値が低くなります。 基準が厳しくなることは必ずしも悪いことじゃなですが、それもある程度UA値が欲しいなという人に関しては採用することで工夫がないとデメリットになる可能性があると思います。 基礎外断熱に関して1つ追加させてください。 確かにシロアリは怖いですが、コンクリートの外に樹脂を貼るのでコンクリートの酸化防止になります。だから基礎が長持ちするとう利点があります。 これは技術者の中で議論があるところなのでこれを言うと怒る方もいらっしゃるかもしれませんが、床断熱を全面Uの字型にやって断熱材を内側に全部敷き詰めたらどうなるかという実験をやった人がいらっしゃいます。長野の大井建設さんが信州大学の先生と一緒に取り組まれました。 計測によると、計算上は全部敷いた方が保温するということだったんですけど、現実で測ってみたらL型にするのと全面Uの字型に貼るのとでは、ほぼ効果に差がない、あってもごくわずかという結果がでたそうです。 ここでポイントなのは最小限のL型でもそこそこの性能値が出るということです。ここまでが基礎断熱に関しての基本的なメリット・デメリットだと思います。 これから家を建てられる方にお伝えしたいのは、床断熱がダメということではありません。北海道の寒さが厳しい所だと「床断熱の方がいい」と言う技術者の方はとても多いです。なので床断熱=寒いということではありません。 そうすると「どっちが暖かいんですか?」という質問を受けることがあります。これは断熱のスペック次第です。なので基礎断熱だから寒いとか、床断熱だから寒いということはありません。これを知っていただいたうえでトータルに考えて床下利用をしたいのであれば基礎断熱がいいです。特にそういったこだわりはなくてシンプルな形で建てたいのであれば床断熱の方がいいかなと思います。そういった視点で判断していただければと思います。 今回はハード面の話で堅苦しいテーマだったと思いますが、みなさんの家づくりの参考になればうれしいです。 -------------------- ホームページはこちらです。 https://www.m-athome.co.jp/ モデルハウスはこちらです。 https://www.m-athome.co.jp/model_house #モリシタアットホーム #基礎断熱 #床断熱 #気流止め #床下エアコン #姫路 #工務店 #注文住宅 |